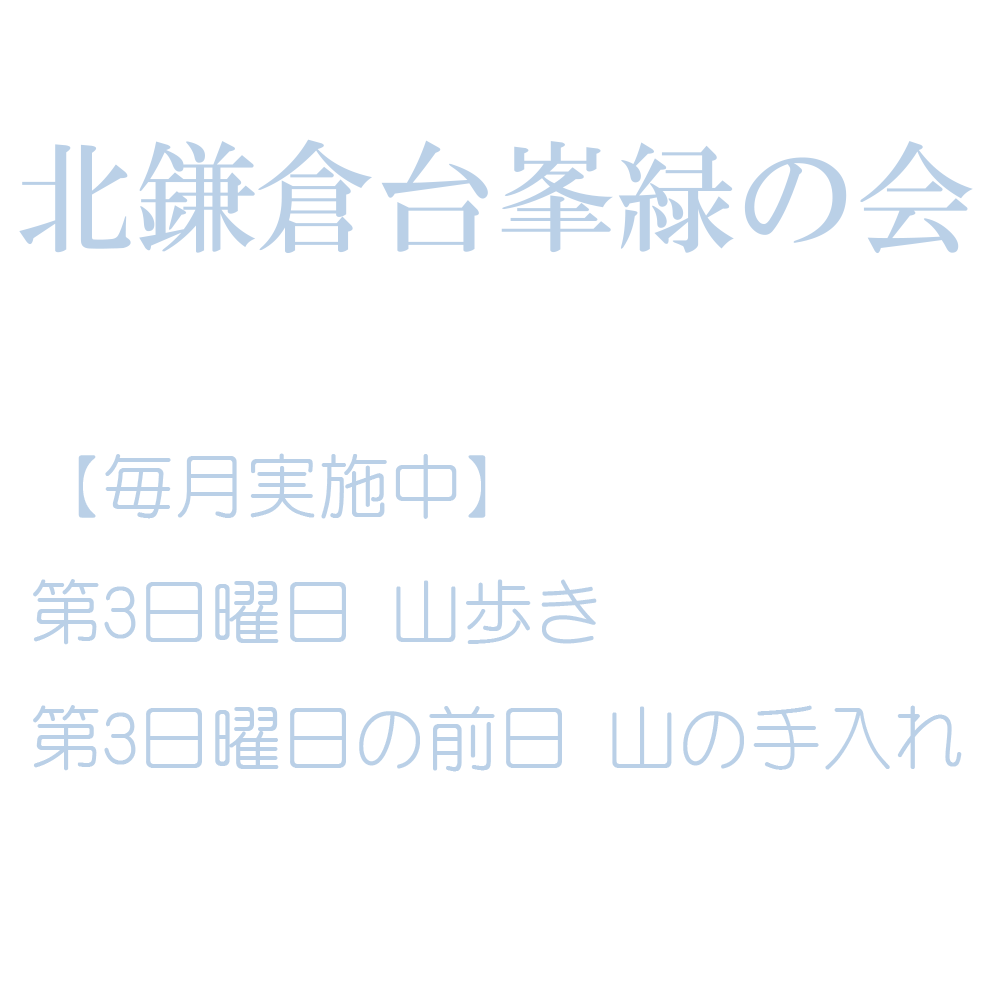読み物
台峯コラム 2025年(令和7年)10月
台峯の周辺 第2期3(通算25) 川は生きている
本田 隆史
そんなテーマの本はなかろう、と思っていた書籍を図書館で発見、驚いた。『鎌倉の川』という、ガリ版刷りの60頁足らずの小冊子だが、更に驚いたのは私の高校の7年後輩8名による研究発表だったことである。発行日は不記載ながら、1976年頃と推測される。その約20年後の同窓会名簿に彼らの名が載っていた。特段関係する職に就いた者はいないようだが、この経験はその後の人生できっと何かの役に立ったことだろう。

内容は、市内の川の流れを一つずつ遡りながら、架かる橋や周辺の寺社などを地理的、歴史的に叙述するが、残念な事に川に生きる動植物については触れられぬ。名前が載る2人の指導教員も、私が生物ではなく歴史や地理を教わった教師だった。また、ほぼ鎌倉地区だけが対象で、例えば扇ガ谷の扇川が付近の寿福寺や上に架かる「勝の橋」などとともに紹介されている。
ところで川にはフタを被せて通行の用などに供されることも多いが、もし暗渠ばかりになっていたら川や橋の調査など意味が薄れ、彼らもその気になれなかったろう。その点この川は今も多くの地点で川面が見え、観察ができる。更に岸辺も自然に優しい土手の箇所があり、実は当会久保幹事が或る団体で生態調査を続けているのも、この川である。
いつだったか私も朝の出勤途中、家近くの流れで長いものが水中を蠢きながら下っていく。朝から蛇とは!? が、ウナギだ!夜エサを漁りに行った帰りか、あとを追うと、とある所で川底の穴に潜っていった。シメタ!週末は蒲焼だ。ところが翌日の大雨で川底の様子が一変、どこだったか不明に。
また、別の朝は、或る家の川を跨ぐ橋桁に工事用虎ロープの切れ端がぶら下がっている。始末の悪い家だ、と思いつつ近づくと、何とオニヤンマである。川から上がり羽化した翅を乾かしている、生まれたての、朝日に輝く黄と漆黒の縞であった。
夏の帰宅時は、ゲンジボタルが舞った。もはや時効と思うが、一頭を幼子のために一晩借りたことがある。暗くした部屋で放すと、光りながらまっすぐに飛び向かった先には同様に黄緑色の光が。エアコンのLED豆ランプである。メスではない、と気づいたのか、飛ぶのを途中で止めたが、現在主流のLED街灯はホタルのためには廃すべきだろう。 また、「芹生ふる辺(へ)にきて流れゆるやかに」は近所の老人による写生句だが、その巧拙はともかく、流れにはセリが生え、その上の崖にはヤマユリも咲く。
ところで、当会が「山歩き」で台峯に向かう道に沿った西瓜川は大船地区のため、冊子には載っていない。が、今も覆いは少なく、川面を覗ける。一山越えても自然は大きくは変わらない。ウナギは潜んでいる筈だし、ホタルは東日本型が現に舞うとのこと。様々な植物が生え、ヤンマも飛ぶ。けれど、同じヤンマでも、コシボソヤンマにはここで初めて私は遭った。細かくは、川はみな異なるのである。
川を加工するのは、このくらいにしたいものだ。歴史や地図の上だけでなく、自然としてそれぞれ今を生きているのだから。
印刷用原稿:川は生きている(PDF版)
北鎌倉台峯トラスト 事務局
照会先(山歩き関係)本田方 電話090-6502-2470
(山の手入れ関係)出口方 電話090-1404-5611